| 技術情報2023/12/07
圧力がかかるダクト設計を進める際、
「角ダクトを極力避けて丸ダクトを使う事」
「角ダクトを使うのであれば補強材を入れる事」
とお客様からご指示を受けます。
補強材の有無でどれほど強度に差が出るか
気になったので構造計算ソフトmidas iGenで
確認してみました。
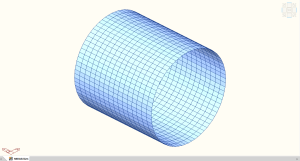
<ダクトA>
直径1500mm、板厚9mmの丸いダクト
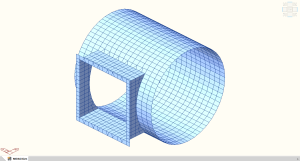
<ダクトB>
ダクトAに横900mm×縦900mm、板厚9mmの
四角い分岐(マンホール)を取り付けたイメージ
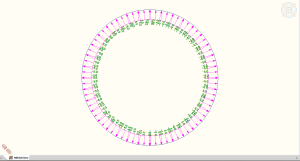 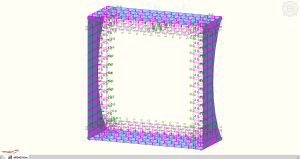
ダクトA、B内面にJIS5k(5kg/cm2)相当の圧力を想定し、構造解析します。
実際にはダクトの固定方法や熱伸び、摩耗代など
考慮すべき条件ありますが割愛させていただきます。
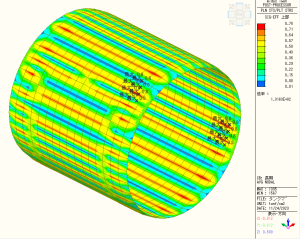 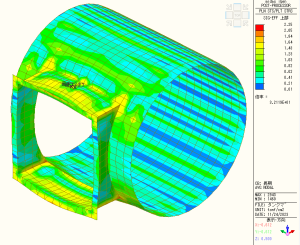
ダクトA「0.78(ton/cm2)」<ダクトB「2.25(ton/cm2)」
画像右上の数値は最大応力(単位面積あたりの内力)を示しており、
四角い分岐が付く前のダクトAに対してダクトBの数値が
約3倍も大きくなっています。
ダクトBの数値はSS400の鉄板で構造物を作る上で
NGとされる目安の値でもあり、これは四角い分岐箇所が
内側からの圧力で破損する危険な状態です。
上記の問題を解決する為、補強材としてリブ板を入れてみます。
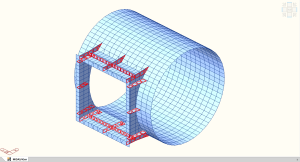
<ダクトC>
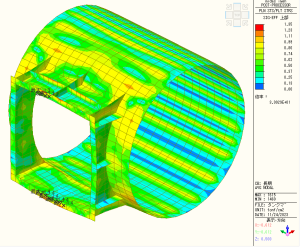
ダクトB「2.25(ton/cm2)」>ダクトC「1.35(ton/cm2)」
角ダクトのフランジ部分に最大応力が発生。
ダクトCの数値はダクトBの0.6倍程度にまで低くなりました。
圧力のかかる丸いダクトに開口をあけたり、丸ダクトに角ダクトを溶接するような
設計を行う時は「同じ板厚だから大丈夫」と安易に考えず、
十分な補強方法を考慮した上で設計するよう気を付けましょう。
設計事業グループ/松下
TECHNICAL ENGINEERING GROUP(設計事業グループ)
|

